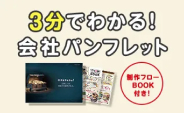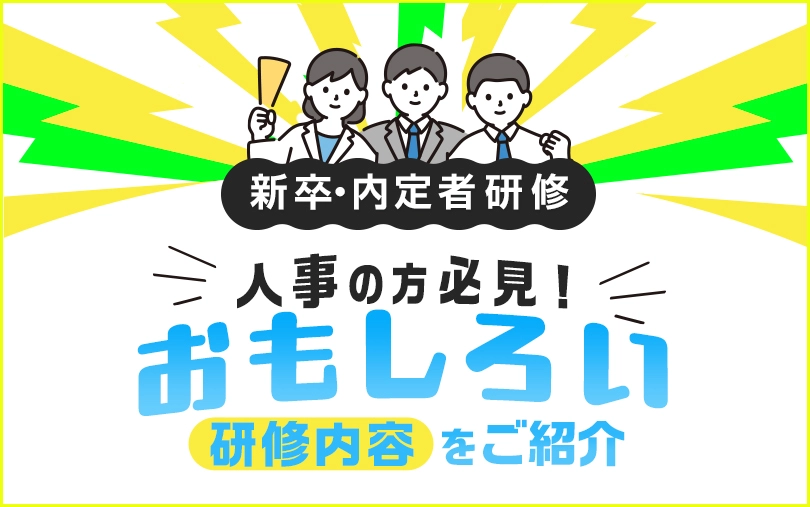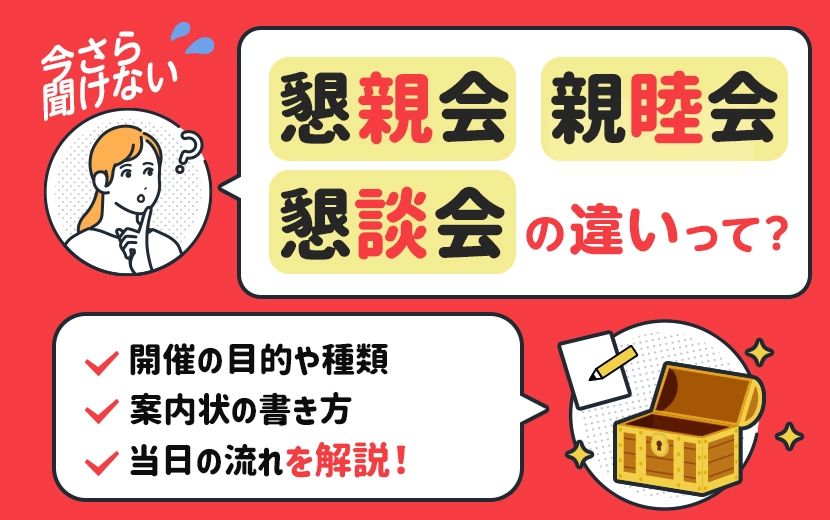BLOG
- 社内イベント
研修とは?意味や目的、種類ごとの実施方法を解説
更新日:2026.01.23

研修は、従業員が業務遂行に必要なスキルや知識を身に付けることを目的とした教育活動です。企業が成長し、発展していくためには従業員の能力開発は必要不可欠です。多くの企業は研修制度を導入し、従業員のスキルアップや知識習得をサポートしています。
この記事では、企業が研修を行う意味やメリット、研修の種類、手法について詳しく解説します。研修を実施する手順や、研修成功のポイントについても掲載しているので、ぜひ参考にしてください。
研修とは
研修とは、従業員が業務を行う上で必要とされるスキルや知識を身に付けるために、勉強会や講座などで学ぶことを指します。研修は新入社員から管理職まで、階層に合わせてさまざまな従業員を対象に行われるのが特徴です。
企業で行う研修方法は、「社内研修」と「社外研修」の2種類に分類できます。以下では、社内研修・社外研修それぞれの特徴を紹介します。
タカラッシュは
\ 謎解き・宝探しの制作実績1万件以上 /
社内研修(内部研修)
社内研修とは、外部講師に委託せずに受講者よりも立場が上の先輩社員が講師をする研修です。社内研修は自社の事業やビジョンに合わせた内容を実施でき、各部署の実情の共有にも役立ちます。
社内研修を行う主な目的は、下記の通りです。
- 自社の理念や事業内容に対する理解を深める
- 現場で役立つ専門知識やスキルを身に付ける
- 社員同士のコミュニケーションを活発にする
社内研修では、自社のミッションやビジョンに沿った研修を行うので、従業員の自社に対する理解を深められます。また、実際に現場で必要となる専門知識やスキルを教育するため、即戦力として期待できるような知識やスキルを身に付けることが可能です。
また、社内研修は社員同士の連携を強化する場としても活用されます。普段の業務では関わりの少ない部署や上司との交流の機会ともなるでしょう。
社外研修(外部研修)
社外研修とは、外部の研修会社や専門家に依頼して実施する研修です。社内研修と異なり、専門分野に特化した講師が行うため、専門的かつ体系的な内容を学べます。
社外研修を行う主な目的は、下記の通りです。
- 社内では得られない専門的な知識やスキルを習得する
- 最新の情報を学ぶ
- 柔軟な発想ができる従業員を育てる
社外研修では、自社と無関係の専門家が講師として研修を行います。そのため、自社にはない専門的な知識やスキルを習得できる可能性が高くなります。
また、外部講師による研修は、社内研修では難しい新たな価値観に触れる機会です。知識やスキルを学べるだけでなく、新しい意見を聞けるため、柔軟な発想ができる従業員の育成に効果的です。
学習・実習・演習との違い
「研修」と似た言葉に「学習」「実習」「演習」がありますが、それぞれの意味は異なります。
学習は知識や情報を幅広く吸収する行為全般を指し、講義や読書などを含みます。実習は現場や対象を実際に扱って体験的に学ぶ活動で、教育実習や医療現場での臨床実習が代表例です。演習は、想定状況での訓練やゼミ形式の授業のように、課題解決や実戦的な練習を通じて習熟度を高める取り組みを意味します。
これに対して研修は、従業員が業務に必要な知識やスキルを計画的に身につけるために行われる教育活動を指します。新入社員から管理職まで、階層や役割に応じて内容が設計される点が特徴です。
つまり、学習=基礎的なインプット、実習=現場での体験、演習=実戦的な練習に対し、研修=職務能力を体系的に強化する仕組み、と整理できます。
研修に意味はない?研修をする目的やメリット
企業で研修を行うことは、意味がないと言われる場合もあります。しかし、研修は企業にとっても従業員にとっても多くのメリットがあります。
以下では、研修を行う目的やメリットを社員側と企業側にわけて解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
タカラッシュは
\ 謎解き・宝探しの制作実績1万件以上 /
社員が研修を受けるメリット
社員が研修を受けるメリットとして、自己成長や学びの機会が得られることが挙げられます。研修では、企業で働く上で必要になる専門知識やスキルを学びます。業務の初心者でも新たな知識を得られるため、自己成長のよい機会となるでしょう。
また、研修に参加すると、市場価値が高まるのもメリットの1つです。研修を通じて得た知識やスキルを活用して新しい課題に挑戦すると、自身の専門性や価値を高められます。専門性や価値が高い社員は、より高度な業務に取り組め、企業からも重宝される人材となります。
企業が研修をする目的・メリット
社員が研修によって専門知識やスキルが身につくと、業務効率が上がります。また、社員のモチベーションも向上するため、生産性アップにつながります。
また、リスキリングの機会を作れるのも企業が研修をする目的・メリットです。リスキリングとは、技術革新やビジネスモデルの急速な変化に対応するために、新たな知識やスキルを学ぶことです。
研修によってリスキリングの機会を増やすと、自社の業務に精通した人材を育成できるため、採用コストの抑制などにもつながります。
研修の種類【特徴や狙い】
社員研修は、ターゲットとする社員の階層や職種、研修のテーマなどの切り口から大きく3つに分類できます。
それぞれの研修の特徴や主なカリキュラムなどを順番に解説します。
階層別研修
階層別研修は、従業員を役職や年齢、勤続年数などいくつかの階層に分けて実施する研修です。
階層が変わると、求められる役割も変化するのが一般的です。それぞれの階層の業務に必要な知識やスキルの習得を目的として、階層別研修は実施されています。
階層別研修の主なカリキュラムは、下記の通りです。
| 新入社員研修 | 主に社会人としての基礎知識が不足している新卒の社員を対象としており、ビジネスマナーやコンプライアンス、業務に必要な知識の習得などを目指します。 |
| 若手社員研修 | 若手社員は責任のある仕事も任されるようになるため、業務のための知識やスキル向上を目的とした研修を行います。 |
| 中堅社員研修 | 中堅社員は管理職と現場の仲介役を務める機会が多くなるのが特徴です。リーダーシップやアンガーマネジメントなど、チームで成果を上げるための知識の習得を目指します。 |
| 管理職研修 | 管理職は組織マネジメントやリスクマネジメントなど、チームリーダーとして従業員をまとめるためのスキルを習得します。 |
| 役員研修 | 役員に求められることは、問題解決のための仕組み作りや全体的な視点での問題発見力です。コンプライアンスや経営について学ぶ研修が実施されます。 |
業務・職種別研修
業務・職務別研修は、それぞれの職種の業務を行うために必要な知識やスキルを身に付けるための研修です。職種によって行う業務は異なるため、職種に合わせた研修を実施する必要があります。
業務・職種別研修のカリキュラムの一例は、下記の通りです。
| 営業職向け研修 | 営業職は人と接する業務が多いため、対人スキルの向上を目指す研修を行います。また、問題解決能力やプレゼンテーションスキルの向上を目指す研修も実施されています。 |
| 人事職向け研修 | 人事の業務は、社員の評価や育成、採用などが一般的です。そのため、労務管理や採用研修など、人材に関わる知識やスキルの習得を目指します。 |
| マーケティング職向け研修 | マーケティングは、商品販売のために市場調査や戦略立案などを行う能力が求められるでしょう。リサーチ研修やマーケティング研修などで、効率的な商品販売に必要なスキルを身に付けます。 |
スキル・テーマ別研修
スキル・テーマ別研修は、職種や階層に拘らず特定のスキルやテーマを学ぶ研修です。多くの企業では、自社の課題に合わせて研修のスキルやテーマを決め、階層別研修と業務・職種別研修とを併用して行っています。
スキルやテーマ別研修の一例を紹介します。
| ビジネスマナー研修 | 敬語の使い方や電話対応、名刺交換の方法など、社会人として必要な知識を学ぶ研修です。 |
| コミュニケーション研修 | ビジネス上のコミュニケーションを円滑にし、相手と良好な関係を構築するためのスキルを学びます。ビジネスをする上で、関係者や取引先との良好関係の構築は不可欠と言えるでしょう。 |
| コンプライアンス研修 | 企業が守るべき法令や社会的ルールなどを学ぶ研修です。モラルや倫理観のある行動を意識づけ、従業員の法令順守の徹底を周知することを目的としています。 |
研修の主な手法【簡単な説明・メリット・デメリット】
社員研修にはさまざまな手法があり、それぞれ異なったメリット・デメリットを持ちます。社員研修は、研修で扱うテーマやスキルに合わせた手法を選ぶことが大切です。
なぜなら、学びに適した手法は従業員が知識やスキルを効率的に取り入れることができ、研修の効果が大きくなると考えられるためです。
以下では、それぞれの手法の特徴とメリット・デメリットを紹介します。
タカラッシュは
\ 謎解き・宝探しの制作実績1万件以上 /
OJT(On the Job Training)
OJTは、教育担当者が研修の受講者に日常業務を行わせながら、マンツーマンで指導する研修手法です。「やってみせる」「説明する」「やらせてみる」「確認・追加指導」と4段階にわけて教えるのが基本的な手順とされています。
OJTのメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|
|
OJTは、日々の業務を行うために必要な知識やスキルを身に付ける研修なので、企業全体の理解を深めるには不向きです。企業理念や業務全体の流れなどの共有には、ほかの研修も併用して行う必要があります。
OFF-JT(OFF-the Job Training)
OFF-JTとは、職場ではない別の場所で行うセミナーや研修を指します。職場外でビジネスに関する基本的な知識を学び、配属後にスムーズに業務に取り組める人材の育成を目指す人材育成の方法の1つです。
OFF-JTは、講義形式で研修を行うのが一般的です。専門家から知識やスキルを学べるため、効率的にスキルアップを目指せる方法と言えるでしょう。
OFF-JTのメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|
|
OJTは、日々の業務を行うために必要な知識やスキルを身に付ける研修なので、企業全体の理解を深めるには不向きです。企業理念や業務全体の流れなどの共有には、ほかの研修も併用して行う必要があります。
e-ラーニング
e-ラーニングは、動画や問題集などの教材コンテンツを、デジタルツールを通じて学ぶ研修の手法です。
e-ラーニングの利用者は、用意された教材コンテンツをパソコンやスマホで閲覧し、新しい知識やスキルを習得可能です。また、学習管理システムを利用すると、管理者から教材コンテンツの提供や学習進捗の確認、評価などを行えて、研修効果の確認にも役立ちます。
e-ラーニングのメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|
|
e-ラーニングは、文字だけでなく映像やアニメーション、CGなども活用しながら知識を深められます。ただし、対面での研修ではないことから、実技を学習する場合は工夫が必要です。
オンライン研修(Web研修)
オンライン研修は、Web会議ツールなどを利用して、オンライン上で開催される研修です。開催日時が事前に決まっており、リアルタイムで行われるのが一般的です。
オンライン研修は、パソコンやスマホを利用して学習するという点で、e-ラーニング研修と似ています。しかし、オンライン研修は、講師と受講者がリアルタイムでコミュニケーションが取れる点がe-ラーニング研修と異なります。
オンライン研修はオンライン上で行われるため、実技を伴う研修には工夫が必要な場合があります。
オンライン研修のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|
|
グループワーク
グループワークは、研修参加者を複数人のグループにわけて議論やプレゼンなどの作業を行う研修です。
グループワークは、アウトプットの質を高めたり、チームビルディングを行ったりする目的で活用されます。グループワークで行う内容は、謎解きや宝探しゲームなどのユニークなものもあります。
| メリット | デメリット |
|
|
最近では、従来のグループワークに加え、謎解き宝探しのような参加型のプログラムも注目されています。こうしたユニークなアクティビティをグループワークに取り入れることで、参加者が能動的に学べる場を提供できるため、新たな選択肢としておすすめです。
また、グループワークは新卒・内定者の研修にも用いられており、内定者同士の関係性を深める良い機会となります。面白くて印象に残る研修内容をお探しの人事担当者の方は、ぜひ以下の記事も併せてご覧ください。
研修を実施するときの手順
研修を実施する際には、基本的な手順を理解しておくことが大切です。手順を理解しておくと、効率よく研修計画を立てられます。
研修を実施するときの手順は、下記の通りです。
| 1:研修の目的・目標を決める |
| はじめに、研修の目的や目標を決めます。研修の方向性を決める際には、企業の経営目標と現状のギャップを確認し、課題を洗い出すとよいでしょう。人事・経営・現場それぞれの課題を抽出すると、研修目標が明確になります。 |
| 2:研修のターゲットを決める |
| 次に、研修のターゲットを決定します。研修を受けるターゲットによって、必要な研修内容は異なります。そのため、階層や職務・職種などでターゲットを絞り込むことは不可欠です。 |
| 3:社外研修・社内研修のどちらにするか決める |
| 社外研修・社内研修のどちらにするのかは、研修の計画段階で決めておく必要があります。社外研修・社内研修の目的やメリットは異なります。2つの研修を比較して、研修の方向性に合ったほうを選択しましょう。 |
| 4:スケジュールを調整して事前告知する |
| ある程度研修の内容が決まったらスケジュールを調整し、社員に事前告知を行います。研修の日時を決める際には自社の年間スケジュールを確認し、実施時期が限られている研修を優先的に決定します。 |
| 5:研修を実施し、効果測定する |
| 研修当日は、計画していたスケジュール通りに進めていきましょう。研修終了後、研修で学んだことが生かされているかどうかの確認も重要です。受講者に対して評価やテストなどの実施が望ましいでしょう。 |
研修のときに押さえておきたいポイント
研修は実施して終わりではなく、計画から振り返りまで一貫した取り組みが求められます。
以下に、成功させるための重要な視点を整理しました。
- 研修コストを把握し、効果と結びつける
費用は直接・間接コストを含め算出し、KPIと結びつけて費用対効果を検証する。 - スケジュールを最適化する
目的や対象に応じて時期・期間・頻度を調整し、最適なタイミングで実施する。 - 社内研修と社外研修をバランス良く使い分ける
社内は低コストで自社文化に即し、社外は専門性強化に有効で、併用が効果的。 - 進行中のモニタリングとサポート
小テストや観察で理解度を把握し、即時対応や指導体制の工夫で質を高める。 - 全体を振り返り、次回につなげる
定期的な再確認とフィードバック活用で学びを定着させ、改善に活かす。
研修コストを把握し、効果と結びつける
研修を企画する際には、講師料や教材費といった直接的な費用だけでなく、受講中に業務を離れることによる機会損失や、運営スタッフの労務コストなど間接的な支出も含めて算出する必要があります。
費用面を明確にしたうえで、研修によって達成したい成果やKPI(例:離職率改善、業務効率化、顧客満足度向上など)と結びつけて評価基準を設定することが大切です。高額なプログラムを選んだからといって必ず成果が出るわけではなく、自社の課題に合致した研修かどうかが成否を分けます。
複数の研修サービスを比較し、プログラム内容・受講形式・受講後のフォロー体制を検討したうえで導入することで費用対効果を高められます。また実施後に効果測定を行い、数値と受講者の声の両面から検証することも重要です。
スケジュールを最適化する
研修は実施時期や期間、頻度によって成果が大きく左右されます。
新入社員研修は入社直後に短期間で集中的に行うことで基礎知識を早期に定着させられます。一方の管理職研修やリーダーシップ研修は、数カ月単位で繰り返し学びを実践に移す設計の方が効果的です。また業務が繁忙期に行うと参加者の集中力が途切れやすく、学習効果が薄れる恐れがあります。
年間スケジュールの中で余裕のある時期を選び、受講者の負担を軽減する工夫が必要です。さらに1回あたりの研修時間を長時間にするか、短時間を複数回に分けるかも内容に応じて調整します。たとえば実務スキルは短時間を積み重ねる方が定着しやすく、マネジメントスキルは長期的なケーススタディで学ぶ方が効果的です。
社内研修と社外研修をバランス良く使い分ける
社内研修は自社の理念や業務に即した教育ができ、コストも抑えやすい点が強みです。新人向けに自社の文化や価値観を浸透させる際には特に有効で、現場で活躍する先輩社員が講師となることでリアリティのある学びが得られます。
一方で社外研修は、外部の専門家から最新の知見や業界動向を学べることが大きなメリットです。社内にはない視点を取り入れることで、参加者の柔軟な発想や新たな問題解決力を育む効果も期待できます。
重要なのは、どちらか一方に偏らず、目的や対象者に応じて両者を組み合わせて活用することです。たとえば新人は社内研修で業務の基礎を学び、中堅社員は外部セミナーで専門性を高め、管理職は両方を織り交ぜて組織マネジメント力を強化する、といった形です。
社内・社外を適切に補完し合うことで、組織全体のスキル底上げにつながります。
進行中のモニタリングとサポート
研修を計画通りに進めるためには、実施中のモニタリングが欠かせません。受講者の理解度を小テストやワークの成果物で確認したり、講師が直接質問を投げかけて反応を観察したりすることで、その場で状況を把握できます。
グループワークでは、発言回数や役割分担の様子を観察し、積極性や協調性の偏りがないかをチェックすることも有効です。OJTの場合、指導担当者に過度な負担がかからないよう、チェックリストを活用したり、複数人で指導を分担する体制を整えたりすることが望まれます。
問題が発生した場合にその日のうちに修正できるかどうかで、学習体験の質は大きく変わります。また、研修後に短時間の振り返りを入れると理解度がさらに深まります。
全体を振り返り、次回につなげる
研修は終了後の振り返りによって定着度が決まります。学習した内容は時間が経つと忘れやすいため、研修直後だけでなく1週間後・1カ月後などのタイミングで再確認の機会を設けることが効果的です。
たとえば簡単な課題を出して業務に応用してもらい、次回の研修や会議で成果を共有させる方法があります。アンケートや面談で集めたフィードバックを分析し、次回の研修内容や運営方法に反映させることも重要です。さらに結果を参加者や上司と共有することで、学びを日常業務に結びつける意識が強まります。
報告書やフィードバック資料として振り返りを記録することで、次回の改善に活用できるだけでなく、組織全体にナレッジが蓄積される効果も期待できます。研修を単発で終わらせず、継続的に改善を重ねることで教育の質が高まり、企業全体の成長につながります。
タカラッシュが行った企業研修の事例
下記では、タカラッシュが行った企業研修の事例を2つ紹介します。

株式会社メディクルードでは、自社の20周年および25周年を祝った社員旅行で、部署を超えた組織力を向上させるためにタカラッシュのリアル宝探しを研修として実施しました。
ゲームの問題には工夫を施し、チーム全員でないとゴールできない状況を設定しています。研修が各チームでコミュニケーションを取るきっかけとなり、参加者からも好評を博した研修となりました。

共同カイテック株式会社では、5か年計画の発表時に社員と役員とのコミュニケーションを図る目的でタカラッシュのリアル宝探しを研修として実施しています。宝探しの登場人物として役員を組み込み、社長が映像で登場したり、コスプレをした役員が登場したりと親近感を演出しました。
研修終了後は、ほかの社員から食事に誘われる機会が増えた役員もおり、世代や階層を超えたコミュニケーションのきっかけとなる研修でした。
まとめ
従業員にとって、研修は自己成長し、自分の市場価値を向上するチャンスです。一方で企業も研修を行うことで、生産性の向上やリスキリングによる業務効率化などの効果に期待できます。研修の手法にはOJTやOFF-JT、e-ラーニングなど多様なため、研修目的や対象者に合った手法を選びましょう。
また、タカラッシュが行ったリアル宝探し研修の事例のように、創意工夫を凝らした研修は社員のモチベーション向上や組織力の強化につながります。
タカラッシュのリアル宝探し研修は、ゲームを通じてチームで課題をどのように解決するのか、課題にどう関わるべきか自発的に考えて動く力を養う研修です。受け身の研修と異なり、能動的に目標を達成する喜びに気付ける特徴があります。研修内容をお探しの人事担当者の方は、以下の記事も併せてご覧ください。
タカラッシュは
\ 謎解き・宝探しの制作実績1万件以上 /