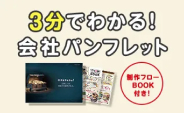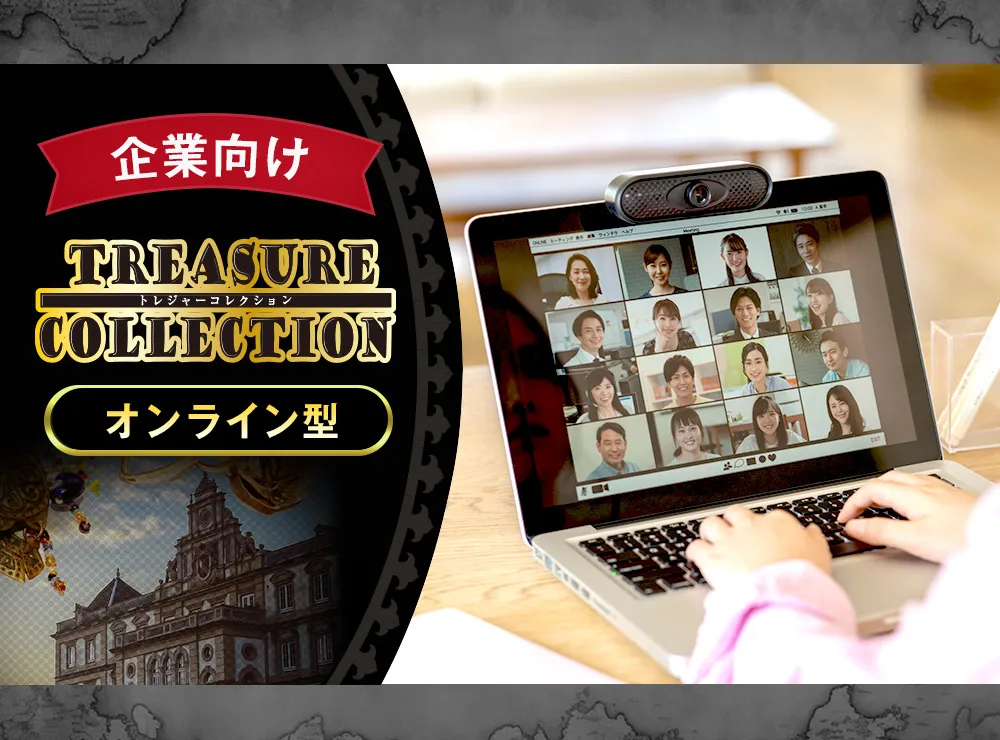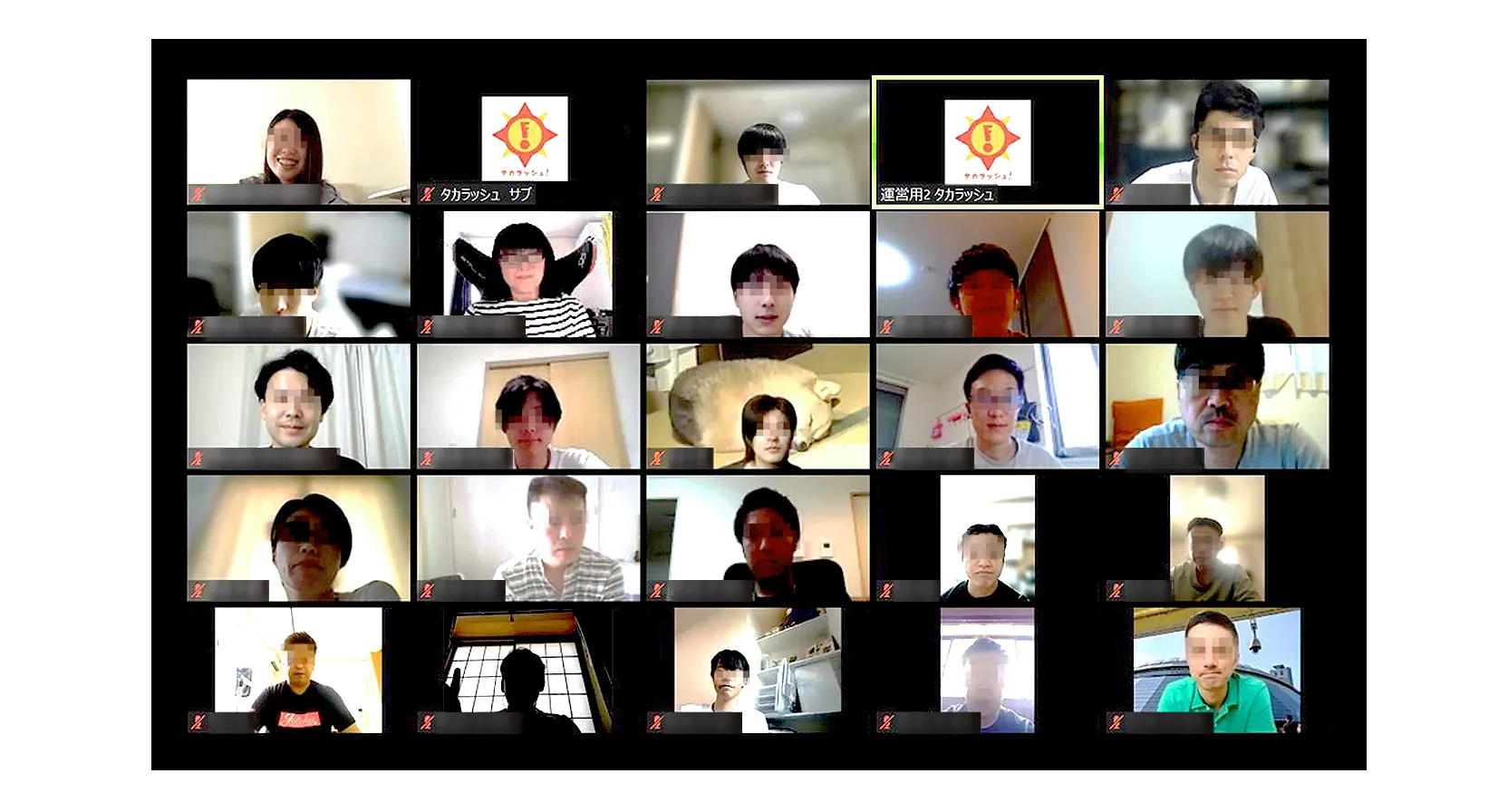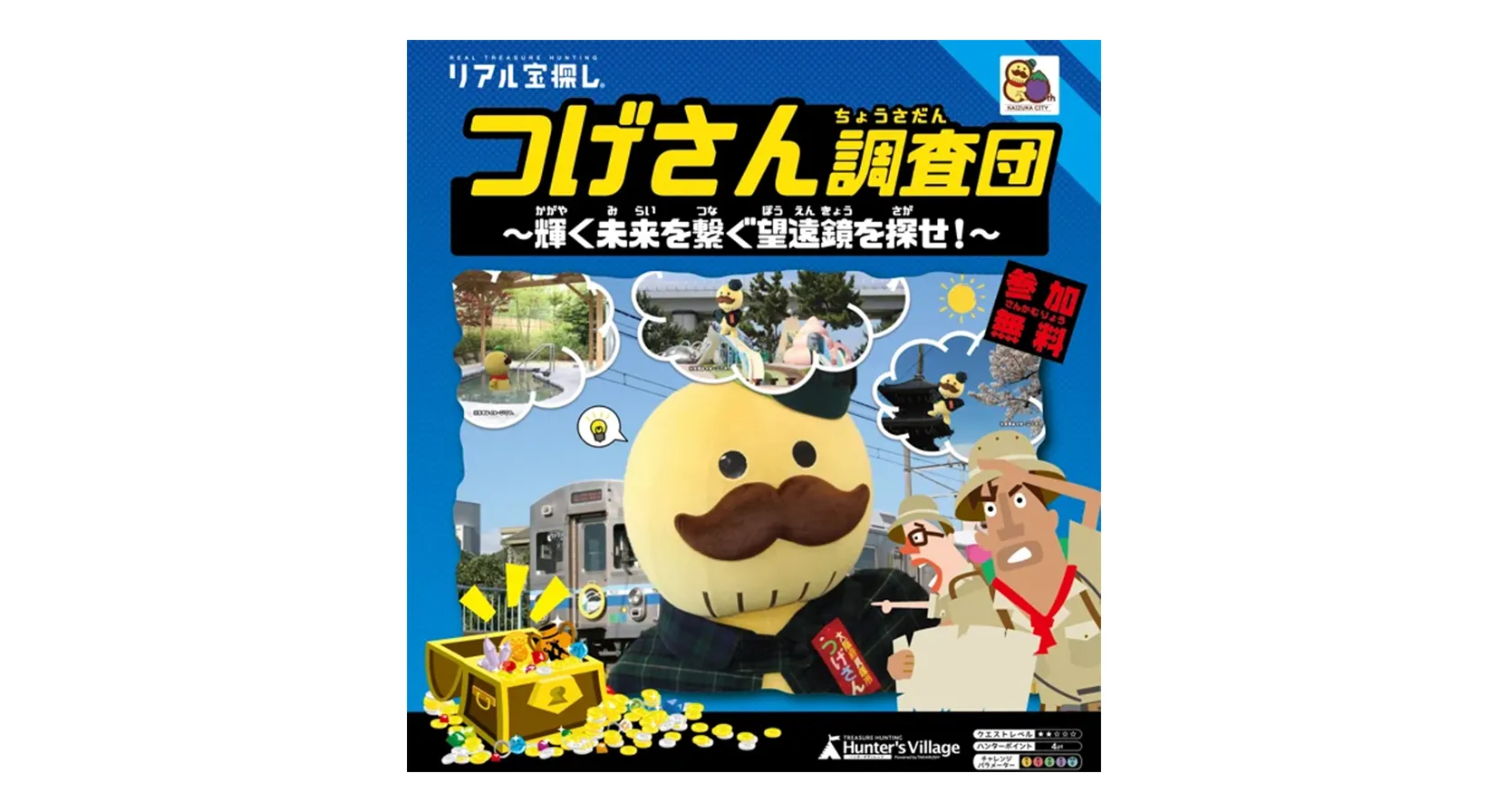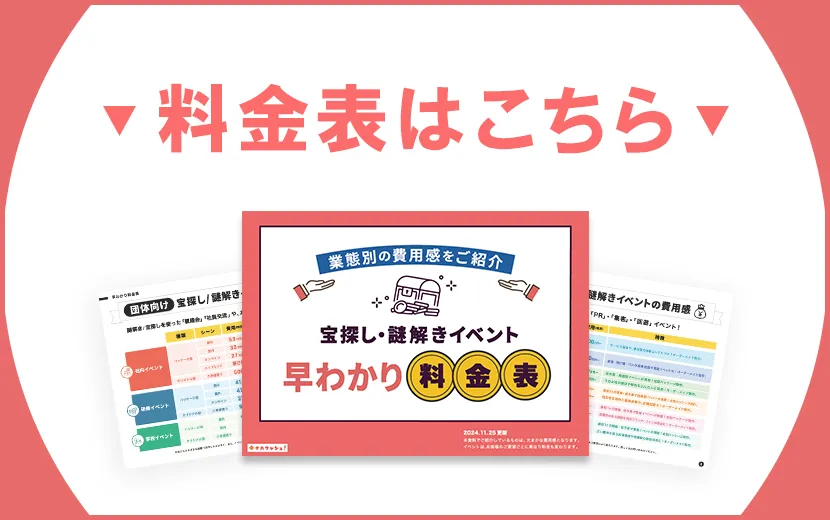BLOG
- 社内イベント
懇親会とは?読み方・意味・当日は何をするのか・マナー(服装など)を解説
更新日:2025.11.21

懇親会とは、職場やコミュニティ内の参加者が親交を深めるために開催されるカジュアルな交流イベントです。
通常、食事や飲み物を囲んで自由に会話を楽しむ場が設けられ、参加者同士がより親しくなることを目的としています。懇親会は、初対面の人々が親睦を深める絶好の機会であり、仕事や趣味に関する情報交換も活発に行われるのが特徴です。
当記事では、懇親会と親睦会・懇談会の違い、社員懇親会や内定者懇親会といった懇親会の種類、懇親会当日の主な流れ、さらに案内状・お礼メールの書き方とマナーを解説します。
懇親会とは?ただの飲み会ではない?(読み方・意味・目的)
読み方: こんしんかい
懇親会とは、参加者同士が打ち解け、親睦を深めたり情報交換したりすることを目的として開催される交流会を指します。単なる飲み会ではなく、組織やコミュニティの結束を高め、円滑な人間関係を築く場として位置づけられています。
料理を囲んで歓談する流れが一般的で、簡単なゲームを楽しむ場合もあり、カジュアルな雰囲気です。近年はオンライン懇親会も開催されるようになりました。似たような言葉に親睦会や懇談会があるため、懇親会との違いがよく分からない方もいるでしょう。ここでは、懇親会と親睦会・懇談会の違いについて解説します。
タカラッシュは
\謎解き・宝探しの制作実績1万件以上 /
親睦会との違い
読み方: しんぼくかい
懇親会と親睦会は同じような意味を持つ言葉ですが、以下のような違いがあります。
- 懇親会
現時点ではそれほど親しくない間柄の参加者たちが、食事を囲んで話したり情報交換をしたりして親交や結束を深める会
- 親睦会
現時点ですでに交流がある参加者たちが、さらに親交を深めるための会
ただし、両者は厳密に使い分けされているわけではありません。仮に、親しい関係者同士で集まる会を懇親会と呼んでも、大きな問題になることはないでしょう。
懇談会との違い
読み方: こんだんかい
懇談会は、特定のテーマに沿って話し合うことが目的の会です。懇親会ほどカジュアルではありませんが、会議ほどかしこまった雰囲気もないことが一般的です。
会社では職場懇談会、学校では教師と生徒、保護者を交えて行う三者懇談会やクラスの課題を話し合う学級懇談会などがあります。
懇親会の種類
懇親会は、主催する組織や集団に応じていくつもの種類があります。たとえば、主催者が会社であれば社員懇親会や内定者懇親会、地域の自治会であれば地域懇親会などです。
ここでは、主な種類別に開催の目的や参加者などについて解説します。
タカラッシュは
\謎解き・宝探しの制作実績1万件以上 /
【会社】社員懇親会
社員懇親会は、会社が複数の部署やチームの従業員を集めて開催する会です。主な開催目的は以下の通りです。
- 職場やチーム内のコミュニケーションを活性化し一体感を高める
- 他部署からの異動や中途採用で新しく加わったメンバーと関係を構築する
- 社員のガス抜きやストレス発散の場を設ける
組織が利益を生むためには、社員が同じ方向を向いて業務に取り組むことが欠かせません。そのためには、社員同士で活発なコミュニケーションが取れる関係の構築が不可欠です。
社員懇親会は、既存社員や新入社員が互いを知り、円滑にコミュニケーションが取れる関係を築くことを目指して開催されます。その点で、食事会や飲み会とは異なります。
【就活】内定者懇親会
内定者懇親会は、内定を出した学生や新入社員を対象として開催する会です。内定者たちの入社意欲を高めるため、以下のような目的で開催されます。
- 内定者に入社前の会社の雰囲気や社風を知ってもらう
- 内定者同士で親睦を深め、入社前から仲間意識を持ってもらう
- 会社に知り合いをつくることで、入社や仕事に対する緊張や不安を和らげる
入社後に自分が働くイメージをつかみやすいように、内定者だけではなく年齢の近い若手からベテランまで既存社員にも参加してもらうケースが一般的です。
【地域】地域懇親会
地域懇親会は、地域のために活動する方が参加し親交を深める会です。自治会や町内会、子ども会、PTAなど地域の組織に所属するメンバーが対象で、以下のような目的で開催されます。
- お互いの顏や存在を知り交流することで、地域で問題が起こったときに協力して解決しやすくする
- 協力してイベントを実施できる下地をつくり、地域活性化を図りやすくする
地域懇親会以外にも、地域の特性を生かしたイベントを実施して企業PRにつなげた事例も数多くあります。詳しくは以下のリンクをぜひご参照ください。
【学校】保育園・幼稚園・学校の懇親会(懇談会・保護者会)
園や学校に子どもを通わせている保護者を対象に開催される会です。
主に以下のような目的で開催されます。
- 保護者同士の交流
- 先生との意見交換
保護者側にとっては子どもの友人の親御さんと直接話す機会が持てたり、先生から教育や子育て、成長に関するアドバイスを得られたりする有意義な時間です。先生にとっても、担当する園児や児童の保護者の人となりや考え方を知る機会になります。
保育園や幼稚園以外でも、大学の新入生向けのオリエンテーションでイベントを活用して交流促進につなげた事例があります。イベントの詳細は、以下のリンクをご覧ください。
懇親会当日の主な流れ
種類によって細部に違いはあるものの、懇親会のおおまかな流れはほぼ同じです。ここでは、一般的な進行の流れを紹介します。
- 開会の挨拶
まずは、司会から開会の挨拶です。最初に会への参加に対してお礼を述べます。その後、主催する目的を簡単に伝え、開会宣言をします。 - 主催者・来賓の挨拶・乾杯
次いで、会の代表者など、主催者の中で上位の立場にあたる人から挨拶をします。もう一度参加者にお礼を述べ、手短に挨拶します。来賓を招いている場合は、代表者挨拶の後に一言いただくケースが一般的です。その後、参加者全員に起立をうながし、乾杯します。 - 食事・歓談
乾杯が終わったら、参加者に自由に食事や歓談を楽しんでもらう時間です。 - 閉会の挨拶
最後に閉会の挨拶をして終了します。会社の懇親会では手締めで閉会するケースも少なくありません。手締めとは掛け声に合わせて手拍子を打つ風習で、1本締めや3本締めがあります。二次会を予定している場合は、挨拶のときに会場や時間を案内します。
飲食と歓談を楽しむだけでは、顔見知り同士で集まってなんとなく会話して終わる可能性があります。それでは親睦を深めるという会の目的が果たせません。そこで、食事・歓談タイムを2回に分け、間にゲームやレクリエーションを楽しむ時間を企画するのもおすすめです。
余興を通して共通の話題ができ、その後の食事・歓談タイムでは初対面だった参加者同士が話しやすい雰囲気になるメリットがあります。実施するゲームやレクリエーションは、シンプルなルールで参加者同士が協力してできるものを選ぶのがコツです。
懇親会のマナー 参加する前に知っておきたいこと
懇親会は楽しく交流する場ですが、最低限のマナーを守ることも大切です。ここでは、気をつけておきたいポイントを紹介します。
- 服装や身だしなみ:清潔感・場に合う装い・動きやすさを意識する
- 席次と座る位置:入口近くは下座、奥は上座という基本を押さえる
- 乾杯や食事の振る舞い:乾杯は全員がそろってから、食事は少量ずつ残さずに
- 羽目を外しすぎない:飲みすぎや大声を避け、節度を守る
- 写真撮影やSNS投稿:必ず許可を取り、個人や場所が特定されないように注意
- 終了時のお礼:主催者や幹事に感謝を伝え、翌日にはお礼メールを送る
服装や身だしなみ
懇親会の服装は「清潔感があること」「場にふさわしいこと」「動きやすいこと」の3つを意識して選びましょう。
会社関係ならスーツや落ち着いたビジネスカジュアル(ジャケット+シャツ、ブラウスなど)が安心です。ジーンズやスウェット、露出の多い服は避けてください。内定者懇親会はスーツが基本ですが、「カジュアルで」と指定がある場合は、ジャケットやカーディガンを合わせたきれいめな普段着を選ぶと好印象です。
学校や地域の懇親会では、普段着に近くても清潔でシンプルな服装が無難です。
夏は汗じみや透けにくい素材、冬は毛玉のないニットなど、季節ごとの工夫も大切です。靴は歩きやすく音が出にくいものを。サンダルや厚底靴は避け、かかとをきちんと整えておきましょう。髪は顔が明るく見えるようにまとめ、爪は短く清潔に。アクセサリーや香水は控えめにして、食事の場に配慮を忘れないようにします。出発前にはしわや汚れを確認し、名札がある場合は左胸に見やすく付けておきましょう。
席次と座る位置
会場に入ったら「入口に近い席が下座、奥が上座」という基本ルールを覚えておきましょう。個室なら奥の壁側が上座、入口に近い通路側が下座です。長テーブルでは、役職者や来賓は中央や奥に、若手や幹事は入口近くに座ります。円卓の場合も入口から遠い席が上座です。立食やビュッフェでも「目立つ場所や中心」が上座と考えられることがあります。
早く着いたときは荷物を広げて場所を確保せず、案内されてから座るのが無難です。席札が置かれている場合は、勝手に動かさず指示に従いましょう。遅れて参加した場合は、まず入口に近い席に座り、幹事の指示で移動してください。
コートや荷物は足元に広げず、壁際にまとめるなど周囲の通行を妨げない工夫を。乾杯の直前はグラスを持って立ち上がり、合図に合わせられる位置にいるとスムーズです。
座る場所に迷ったら「ここでよろしいですか?」と一言聞けば安心です。自分の立ち位置を意識して座ることが、会全体の雰囲気を良くするポイントになります。
乾杯や食事の振る舞い
懇親会の進行は「開会のあいさつ→主催者あいさつ→乾杯→食事と歓談→締めのあいさつ」が一般的です。
乾杯は全員の準備が整ってから行い、グラスは胸の高さで軽く掲げるだけで十分です。強くぶつけるなど、大げさな動作は避けましょう。
お酒が苦手な方はソフトドリンクで問題ありません。食事では取り分け用のトングや箸を使い、少しずつ皿に取ります。ビュッフェでは横入りせず、食べられる分だけを取ることが大切です。残さない量を心がけましょう。着席のときはグラスは右上に置き、食べ終わった皿はまとめておくと片付けやすくなります。
会話は口に食べ物がないときにし、音を立てないよう注意します。乾杯後の個別のあいさつは目上の人から順に短く、グラスは相手より少し低く持つと丁寧に見えます。食事の最中に写真を撮る場合は、料理が運ばれてすぐに短時間で行い、周囲の人やスタッフの動きを妨げないようにしましょう。
飲み物が空きそうな人に「次はいかがですか」と声をかけると好印象です。名刺交換は歓談の序盤や落ち着いた時間に行い、乾杯前や食事中は避けます。
羽目を外しすぎない
懇親会は楽しい場ですが、行きすぎた行動は信頼を損ねます。お酒は自分のペースを守り、最初からハイペースで飲みすぎないようにしましょう。勧められても「今日はゆっくりいただきます」と笑顔で断れば十分です。相手のグラスを無理に空けさせるのもNGです。
大声で騒いだり通路で長時間立ち話をしたりすると、他の人やスタッフの迷惑になるので気をつけましょう。からかいすぎたり写真を勝手に撮ったり、内輪だけで盛り上がりすぎたりするのもマナー違反です。政治や宗教、ギャンブルなどのデリケートな話題は避けると安心です。
喫煙する場合は指定された場所で、同席者に一声かけてから抜けるのがマナーです。余興やゲームは参加したい人が楽しめるように配慮し、苦手な人を無理に巻き込まないようにします。会費や精算は必ず済ませ、忘れ物がないか確認しましょう。二次会に誘われても参加できない場合は「今日はここで失礼します。お声がけありがとうございます」と丁寧に伝えれば問題ありません。
楽しく過ごすことと節度を守ること、この両立が次につながる良い印象を残します。
写真撮影やSNS投稿
懇親会で写真を撮るときは、必ず周りに確認をとりましょう。幹事に「撮影して大丈夫ですか?」と聞くのが安心です。人を撮るときは本人の許可をもらい、無断でSNSに載せるのは避けてください。特に子どもや学生、来賓が写る場合は慎重に扱います。会社や学校の場合は、資料や名札、パソコン画面などが映り込まないよう注意が必要です。スマホの位置情報や自動タグ付けもオフにしておくと安心です。
撮影は料理が運ばれた直後など短時間で行い、他の人やスタッフの動きを邪魔しないようにしましょう。集合写真を撮るときは、係を決めて手早く進めるとスムーズです。「背の高い人は後ろへ」「荷物は足元へ」など一言添えると、全員が気持ちよく写れます。
撮った写真を共有する場合は、社内ツールや限定グループなど、安全な場所にアップするのがおすすめです。SNSに投稿する場合は、個人が特定できない写真を選び、内容もポジティブで簡潔なものにします。場所や個人情報を詳しく書きすぎないことが大切です。
終了時のお礼
懇親会の最後は「きちんとお礼を伝える」ことが印象を大きく左右します。主催者には「今日は貴重な機会をありがとうございました。準備にも感謝いたします」と一言添えると喜ばれます。来賓には「ご挨拶、とても参考になりました」、スタッフには「お世話になりました。料理やサービスも快適でした」と伝えると良い印象が残ります。
会費や精算はその場で済ませ、領収書が必要なら早めにお願いしましょう。忘れ物(名札、スマホ、傘など)がないかもチェックします。翌営業日にはお礼メールを送るとさらに好印象です。件名は「懇親会御礼/氏名」など分かりやすく、本文は「御礼→印象に残ったこと→今後の連携→結び」の流れで3〜5行程度にまとめます。
名刺交換した相手には「昨日はプロジェクトのお話を伺えて勉強になりました」など、個別の一文を加えると関係が深まります。幹事側のときは会場へのお礼や備品の確認をすぐに済ませ、メンバーにも「お疲れさまでした」と声をかけましょう。最後まで丁寧に振る舞うことが、次につながる信頼を築きます。
懇親会で好印象を持たれるためのコツ
懇親会中の表情
懇親会で最初に見られるのは表情です。笑顔は一番の印象アップにつながります。特に意識したいのは「口角を少し上げる」「目元を柔らかくする」こと。緊張して表情が固くなりそうなときは、深呼吸をしてから軽く微笑むと自然に見えます。
相手の話を聞くときはうなずいたり「なるほど」と短い相槌を入れたりすると安心感を与えられます。目線はじっと見すぎず、数秒ごとに目・口元・全体とゆっくり移すと自然です。姿勢も大切で、胸を少し開き、手は机の上に軽く置くとリラックスして見えます。
写真撮影ではあごを少し引き、カメラレンズの少し上を見て笑うと柔らかい雰囲気になります。疲れてきたら飲み物を口に含むときに口角を整えるなど、こまめに表情をリセットする工夫をすると印象を保てます。
懇親会中の話し方
話し方は「短く、わかりやすく、結論から」が基本です。自己紹介は「名前・所属・やっていること・今日の目的・一言」を30秒程度でまとめましょう。
会話では「質問→共感→自分の一言」という流れを意識すると会話が続きやすいです。たとえば「普段はどの地域で活動されているんですか?」などのオープンな質問をすると、相手も答えやすくなります。相手の言葉をくり返してまとめる(リフレーズ)と理解が深まり、会話が弾みます。名前を会話中に1回呼ぶだけでも距離が縮まります。
自慢や否定は避け、意見が違うときは「なるほど、一方で○○~」とやわらかい言葉で伝えると角が立ちません。話を切り上げたいときは「このあとご挨拶したい方がいるので、また後ほど」でスマートに離れられます。最後は「ご一緒できてよかったです」「またお話できればうれしいです」といった前向きな一言で締めると、好印象が残ります。
懇親会の案内状・お礼メールの書き方とマナー
懇親会を開催する場合、幹事は対象者に案内状を送付してお知らせしましょう。懇親会の案内を受け取った場合は速やかに返信します。また、参加した後はお礼のメールを送るのが基本マナーです。
ここでは、案内状や案内に対する返信、お礼メールの書き方について解説します。
案内状の書き方
案内状は、以下のポイントに注意して作成しましょう。
| 社内懇親会 | 社外懇親会 | プライベートな懇親会 | |
|---|---|---|---|
| 送付のタイミング | ・懇親会開催の1~2か月前を目安にする ・遅くとも2週間前までに出す |
||
| 記載する内容 | ・開催の趣旨 ・日程 ・具体的な場所・地図 ・会費額と徴収方法 ・出欠の返事の締め切り日時 ・キャンセルする際の規定 ・問い合わせ先 |
||
| 書く際のポイント | ・メールで案内する場合は「拝啓 ○○の候~」といった挨拶文は省略する ・他のメールに埋もれないよう、件名に「懇親会」と記す |
・フォーマルな会の場合は郵送で送る ・「拝啓」から始まる前文をきちんと記載する ・カジュアルな会はメールでもよく、挨拶文も親しみやすい内容にする |
・SNSで連絡する場合、挨拶は省略してよい |
案内状への返信方法
主催者側の準備があるため、案内状を受け取ったら早めに返信します。以下は、メールで案内を受け取って返信する際の注意点です。
- 件名は書き直さず「Re:」がついた状態のままにする
- メール冒頭には担当者の名前+様を明記する
- 挨拶文は、社内向けは「お疲れ様です」、社外向けは「お世話になっております」とする
- 案内に対するお礼を一言述べる
- 欠席する場合は簡潔に理由を述べて断る
お礼メールの書き方
参加者側は、懇親会に参加した後にお礼のメールを送るのが一般的なマナーです。以下のポイントを押さえ、主催者に忘れず送付しましょう。
- 送付のタイミング
・早ければ早いほどよく、懇親会参加の当日に送るのが理想
・遅くても翌々日までに送る
・会社関係の場合は相手の休日は避け、休み明けの営業時間内に送る - 件名
・件名は相手がすぐに内容を把握できるように「懇親会のお礼」などとする - ポイント
・お礼の言葉と「楽しいひとときが過ごせました」など感想を簡潔に述べる
タカラッシュは
\謎解き・宝探しの制作実績1万件以上 /
まとめ
懇親会とは、仕事や趣味、地域活動などで関わる人々が集まり、親交を深めるためのイベントです。カジュアルな雰囲気の中で、料理や飲み物を楽しみながら、参加者がリラックスして話せる場が設けられます。懇親会の目的は、関係者同士がより良いコミュニケーションを図り、協力関係を築くことです。
「社員が夢中になって参加できるイベントやゲームを取り入れたい」という場合は、タカラッシュのリアル宝探しがおすすめです。リアル宝探しでは大人でもワクワクできる仕組みがたくさんあるので、社員同士の交流活性化だけでなく、組織力向上にも役立ちます。懇親会などの企画としてリアル宝探しに興味がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
タカラッシュは
\謎解き・宝探しの制作実績1万件以上 /