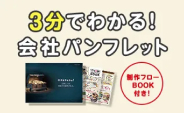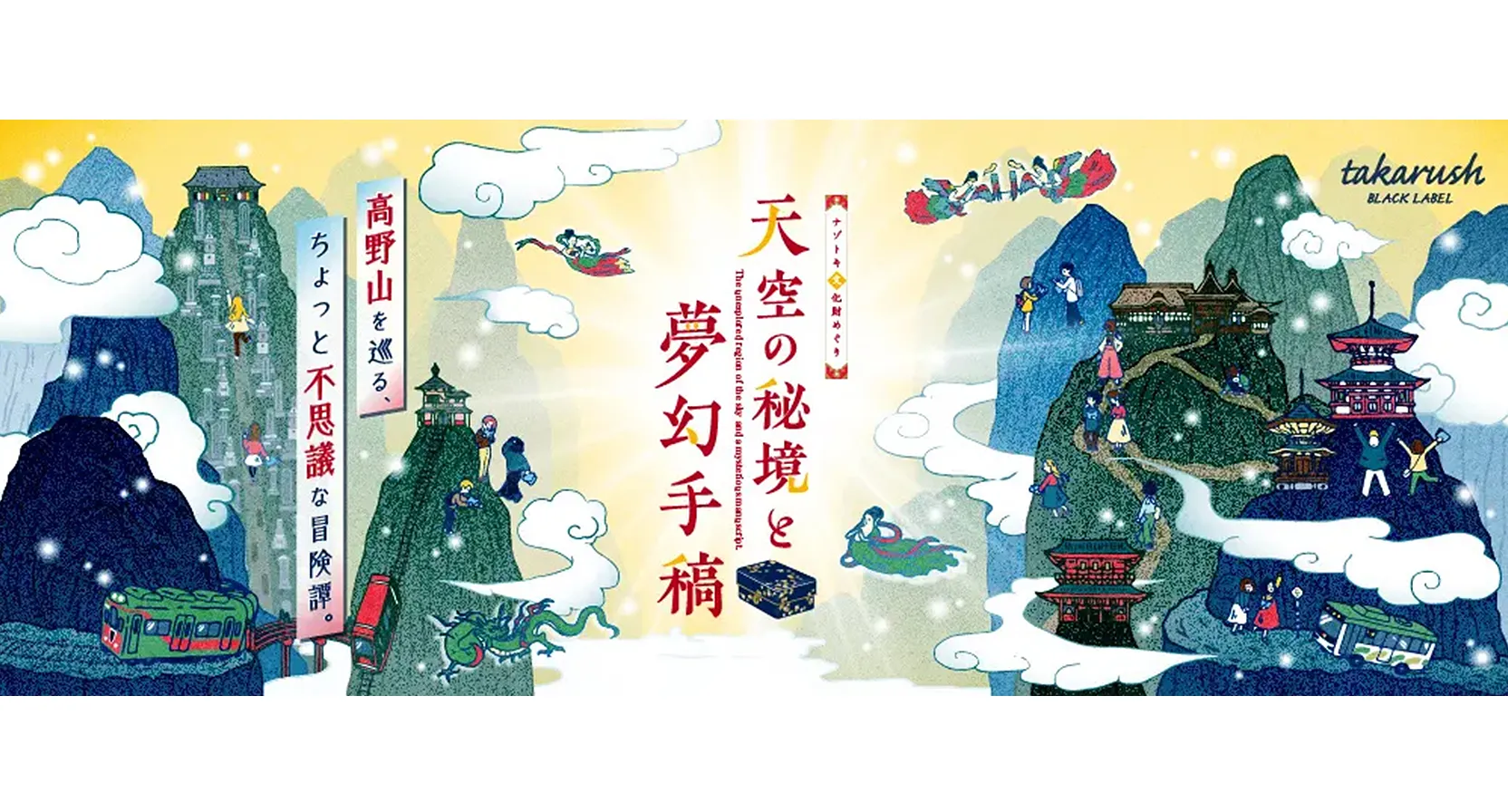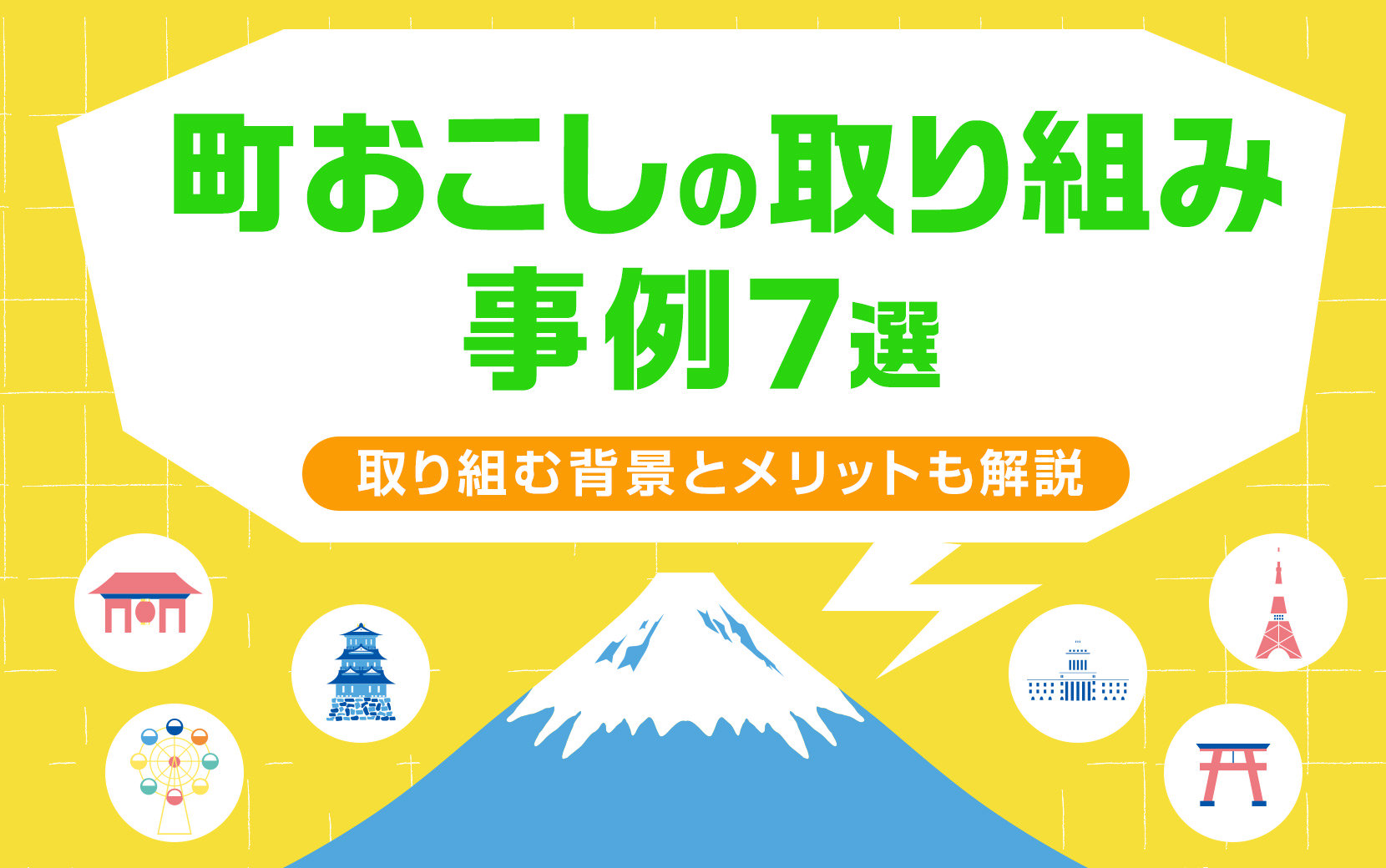BLOG
- 地域活性化
自治体の地域活性化に謎解きイベントを取り入れるメリット・活用事例
更新日:2025.04.27

近年では、各地の自治体が観光資源や歴史的建造物、地元グルメといった地域ならではの魅力を最大限に生かした謎解きイベントを行っています。街歩き型の謎解きは、訪れた方に地域の魅力を「体験」として届ける手段として有効です。物語性のある仕掛けを通じて地域に親しみを持ってもらい、消費行動や再訪につながる好循環を生み出せます。
当記事では、謎解きイベントを地域活性化として活用するメリットや導入事例を紹介します。自治体職員や観光振興担当者の方で、地域活性化としてなにかイベントを開催したいと考えている方は、ぜひご一読ください。
自治体の地域活性化として謎解きを取り入れるメリット
地域活性化とは、地域の経済や文化、コミュニティを活性化させるための取り組みを指します。特に人口減少や観光客数の減少といった課題を抱える自治体にとって、魅力あるコンテンツを通じて地域の価値を再発見してもらうことは重要です。
近年では、地域の名所や歴史的資源を生かした謎解きイベントを企画する自治体も増えており、観光誘致や地域住民の参加意識向上にもつながっています。
地域活性化の手段として注目を集める「謎解きイベント」ですが、なぜここまで人気が広がっているのでしょうか。謎解きの意味合いや背景、種類については、こちらの記事で解説しています。
はじめての謎解きイベントも安心!
\ 謎解き・宝探しの制作実績1万件以上!/
地域の魅力を体験できる
謎解きイベントを取り入れることで、参加者が地域の魅力を体験できるというメリットがあります。自治体が実施する謎解きイベントの多くは「回遊型」と呼ばれ、参加者が商店街や観光名所など複数の地点を巡る仕組みになっています。自然と地域の名所に足を運ぶことになり、その土地ならではの歴史や文化、グルメなどの魅力に触れる機会を創出できます。
「ただ観光する」のではなく、謎を解きながら目的地を巡る体験が、地域との深い接点を生み出します。これにより観光地としての認知度向上だけでなく、リピーターの増加や地域住民との交流促進にもつながる可能性があります。
商店街や地元店舗の活性化になる
地域活性化に謎解きイベントを取り入れると、商店街や地元店舗の活性化にもつながります。特に回遊型のイベントで観光地を巡る仕組みをつくると、参加者が地域内を歩き回る動機が生まれ、自然と地元店舗への立ち寄りや消費が促されます。
イベントと連動して、対象店舗で限定ヒントを配布したり、参加者特典を用意したりする仕掛けを加えることで、店舗への関心も高まります。地域外からの来訪者だけでなく、地元住民にとっても再発見の機会となり、継続的な集客や売上向上につながる点が大きなメリットです。
住民同士の交流促進になる
謎解きイベントは観光客だけでなく、地域に住む人々同士の交流の場としても機能します。イベントを通じて親子や友人同士が協力しながら課題に挑戦したり、地域の風景や歴史を再発見したりすることで、世代や立場を超えた会話が生まれやすくなります。
また、地元の商店や施設が謎解きの舞台となることで、普段あまり立ち寄らない場所にも足を運ぶきっかけとなり、地域内のつながりや理解が深まります。地域のコミュニティを活性化する手段としても、謎解きイベントは有効な施策のひとつです。
地域の歴史・文化の発信ができる
自治体の謎解きイベントは、地域の歴史や文化を伝えるツールとしても活用されています。観光パンフレットや看板では伝えきれないストーリーを、謎解きの仕組みに組み込むことで、参加者は自然と地域の背景や魅力を学ぶことができます。
たとえば、伝統行事や地元の偉人、建造物の由来などを題材にした問題を解くうちに、知識としてだけでなく体験として記憶に残るのが大きな特徴です。楽しく学びながら地域の魅力に触れてもらえるため、郷土愛の醸成やリピーターの創出にもつながります。
SNSで拡散されやすい
謎解きイベントには写真映えするスポットやユニークな仕掛けが多く、参加者が自発的にSNSに投稿したくなる仕組みと親和性が高いコンテンツです。ハッシュタグを活用した投稿やストーリーズでのシェアにより、イベントの様子がリアルタイムで拡散され、無料で大きなPR効果を得られる可能性があります。
特に若年層を中心に、SNSで話題になった地域には「自分も行ってみたい」という動機が生まれやすく、新たな観光客や来訪者を呼び込むきっかけにもなります。口コミや体験談を通じて、地域の認知度向上にも貢献します。
自治体の地域活性化に取り入れる謎解きイベントの種類
自治体が地域活性化を目的に導入する謎解きイベントの多くは、観光地や商店街などを実際に歩いて回る「周遊型」が主流です。参加者が地域に足を運ぶ仕組みをつくりやすく、滞在時間や消費の増加にもつながります。
ひと口に周遊型と言っても、その形式は多様です。以下では謎解きイベントの種類を紹介します。
観光地や商店街を巡る「街歩き型」
街歩き型の謎解きイベントは、観光地や商店街を実際に巡りながら謎を解いていく形式です。歴史的建造物や地域の名所を巡る過程で、その土地の文化や魅力に自然と触れられる点が特徴です。地元のお店と連携し、特典を用意したり買い物を促すような工夫を凝らすことで、地域経済の活性化にもつながります。
スタンプラリーのような形式を取り入れることも多く、誰でも参加しやすいのがメリットです。一方で、屋外での開催が前提となるため、天候に左右されやすいというデメリットもあります。とはいえ、地域の魅力を広く発信しながら楽しめる、人気の高いスタイルです。
複数のエリアを巡る「広域型」
広域型の謎解きイベントは、電車やバスといった交通手段を活用して複数の地域を巡りながら進める形式です。市町村や複数の駅にまたがることもあり、規模の大きさが特徴です。移動を伴うことで地域間の回遊性が高まり、観光客の滞在時間や消費行動の拡大にもつながります。
地域振興や公共交通の利用促進を目的とした鉄道会社や自治体による導入が多く、沿線全体の魅力発信や新たな観光ルートづくりにも効果的です。ただし、移動の負担や交通費の問題もあるため、参加ハードルを下げる工夫が求められます。
AR・デジタル技術を活用した「デジタル型」
デジタル型の謎解きイベントは、スマートフォンのアプリやAR(拡張現実)技術を活用し、現実空間とデジタルを組み合わせて展開されます。参加者は指定されたスポットを巡りながら、画面上に表示されるヒントやキャラクターと連動して謎を解いていきます。
リアルとバーチャルの融合により、臨場感や没入感が高まり、若年層を中心に高い支持を得ています。また、紙の配布物が不要なため運営コストを抑えられる点や、リアルタイムで参加状況を把握できる利便性も魅力です。一方で、スマホの操作や通信環境の整備が参加の前提となるため、デジタル機器の扱いに不慣れな層への配慮も必要です。
自治体の地域活性化の謎解きイベント活用例
タカラッシュでは都道府県から市町村まで、さまざまな地域活性化イベントを実施しています。以下では、地域活性化の謎解きイベントの活用例を3つ紹介します。
タカラッシュと音声ARアプリ「SARF」が展開する『音解きトリップ』は、観光地・江の島を舞台に、音声ARと謎解きを組み合わせた体験型イベントです。松本梨香さんの音声ガイドに導かれながら、41か所の音声スポットを巡り、物語とともに地域の歴史や文化を学べます。視覚に頼らず安全に没入できる点も魅力です。
松本梨香の音声で、
江の島を冒険!新感覚の観光RPGコンテンツ
「音解きトリップ」>>
タカラッシュとJR東海が連携して開催した「迷子の仏像と京都の宝」は、観光キャンペーン「そうだ 京都、行こう。」の特別企画として実施された周遊型謎解きイベントです。京都駅周辺の寺院を巡りながら、LINEアプリを使って謎を解く仕掛けで、参加者は自然と仏像や寺院に親しみ、京都の歴史や文化に触れることができます。子どもから大人まで楽しめる構成と、観光地への経済波及効果を兼ね備えたイベントです。
世界遺産・高野山を舞台に開催された「ナゾトキ文化財めぐり 天空の秘境と夢幻手稿」は、歴史と文化の奥深さを体感できる謎解きイベントです。タカラッシュが制作を手がける大人のための謎解きイベント「takarush BLACK LABEL」シリーズとして、奥之院や壇上伽藍といった文化財を巡りながら秘められた宝の謎を解き明かしていきます。高野山の歴史や宗教文化に触れながら楽しめる点が大きな魅力です。
まとめ
自治体の地域活性化策として注目される謎解きイベントは、観光資源の活用や地域経済の活性化、住民交流の促進など多くの効果をもたらします。街歩き型や広域型、AR技術を活用したものなど形式も多様で、地域の魅力を体験的に伝える手法として全国で導入が進んでいます。
地域活性化の手段として謎解きイベントが注目される一方で、他にもさまざまな町おこしの取り組みが各地で実施されています。具体的な事例を知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
地域活性化として謎解きイベントを開催したいものの、「何から始めたらよいか分からない」「地域の特色をどう生かせばいいのか悩んでいる」そんな方は、これまで1万件以上の謎解きイベントを手がけてきた「タカラッシュ」にご相談ください。
タカラッシュでは20年以上のイベント実施実績で培ったノウハウで、地域活性化や商品PR、回遊促進、集客など、さまざまな課題を解決しています。詳細を知りたい方やご相談がある方は、イベント内容がまだ具体的に決まっていなくても、お気軽に以下のお問い合わせフォームをご利用ください。
タカラッシュは
\ 謎解き・宝探しの制作実績1万件以上!/